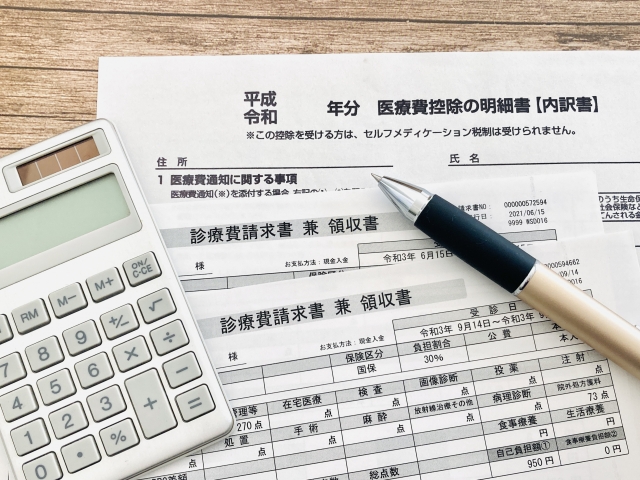2025.8.22 <00880>
はじめに
「日本人が一生にかかる医療費は約2,700万円」という数字を聞いたことがありますか?
これは厚生労働省の推計による平均値で、男女合わせた国民1人あたりの生涯医療費を示したものです。
数字だけを見ると「そんなにかかるの?」と驚くかもしれませんが、実際のところは 公的医療保険制度 や 高額療養費制度 のおかげで、私たちが自己負担するのは総額の一部に過ぎません。
それでも、病気やケガはいつ訪れるかわかりませんし、思いがけず長期入院や高額な治療費がかかる場合もあります。この記事では、
- 生涯医療費2,700万円の内訳
- 年代ごとに増えていく医療費の現実
- 公的制度でカバーできる部分と限界
- 民間の医療保険が果たす役割
を整理しながら、私たちがどのように医療費に備えるべきかを考えていきます。
生涯医療費2,700万円の内訳とは?
厚生労働省のデータによると、男女平均で 一生にかかる医療費は約2,700万円。
内訳をみると、
- 男性:約2,584万円
- 女性:約2,822万円
女性の方が長寿である分、医療費も多くかかる傾向があります。
さらに注目すべきは、医療費の大半が高齢期に集中していることです。
- 65歳以降にかかる医療費 → 生涯医療費の約6割
- 70歳以降だけでみても → 約半分以上
つまり、働いている現役時代よりも、リタイア後にこそ医療費の負担が大きくなるのです。
実際に自己負担するのはいくら?
2,700万円と聞くと途方もない数字ですが、ここで大切なのは 実際に個人が支払う自己負担額。
日本には 国民皆保険制度 があり、医療費の7〜9割は健康保険でカバーされます。
さらに、自己負担が高額になった場合には「高額療養費制度」があり、
月ごとに自己負担額の上限が定められています。
そのため、最終的に個人が負担する額は 平均で500万円前後 とも言われています。
ただし、これはあくまで平均値。
- 長期入院が必要になった場合
- がんなど高額な先進医療を受けた場合
- 介護とのダブル負担が発生した場合
には、想定以上の出費になる可能性があります。
年代別に見た医療費の特徴
40代・50代
生活習慣病が出てきやすく、糖尿病や高血圧などの通院が増える時期。
まだ現役で働いているため、医療費の自己負担割合は3割。
大きな病気をすると収入減と医療費増加が重なるリスクも。
60代
定年を迎え、収入が年金中心になる世代。
医療費の自己負担割合は2〜3割に下がるものの、病気や入院の頻度が増える。医療費と生活費の両立が課題に。
70代以降
加齢による疾病や入院が増加。医療費総額の半分以上をこの時期に費やすとされる。
自己負担割合は1〜2割に軽減されるが、それでも長期入院や継続治療は家計への負担大。
公的制度の強みと限界
公的医療保険や高額療養費制度は、日本の安心の土台です。
しかし、これだけで十分と言えるでしょうか?
強み
- 医療費の大半をカバーしてくれる
- 高額療養費制度で「青天井の医療費」にならない
- 70歳以上は自己負担割合が軽減される
限界
- 入院時の差額ベッド代は対象外(1日5,000〜20,000円程度が自己負担)
- 食事代・生活費は別途かかる
- 先進医療や自由診療は保険適用外
つまり、公的制度で安心できる部分は大きい一方で、
「生活費+医療費+自己負担分」が重なると家計にダメージを与える可能性が残っています。
民間医療保険の役割とは?
そこで登場するのが 民間の医療保険。
「国の制度があるのに、保険って必要?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、以下のようなシーンでは民間保険が家計を守る強い味方になります。
- 長期入院で差額ベッド代がかさむとき
- がん治療で先進医療(数百万円〜)を選択するとき
- 入院により収入が減少し、生活費が不足するとき
- 公的制度ではカバーされない細かい出費(交通費・付き添い費用など)
特に、40代・50代の働き盛り世代にとっては「収入減への備え」と
しての医療保険の意味が大きいです。
医療保険に加入する前に考えるべきこと
- 生活防衛資金があるか?
まずは最低3〜6か月分の生活費を貯蓄で確保。
これがない状態で高額な保険料を払うのは本末転倒です。 - 公的制度を理解しているか?
高額療養費制度を知らずに「医療費は何百万円もかかる」と誤解して加入すると、
過剰な保障になりやすいです。 - 必要な保障を絞る
入院日額をいくらにするか? がん特約をつけるか? 先進医療特約は必要か?
自分や家族のライフスタイル・健康状態に合わせて選びましょう。
まとめ:医療費は「制度+自助+保険」で備える
- 日本人の生涯医療費は約2,700万円
- 実際の自己負担は平均500万円前後
- 高齢期に医療費の大半が集中する
- 公的制度は心強いが、差額ベッド代・先進医療などには対応できない
- 民間医療保険は「家計を守るセーフティネット」
大切なのは、「医療費をゼロにする」ことではなく、無理のない範囲で備えておくこと。
公的制度を正しく理解したうえで、自分に合った保険や貯蓄を組み合わせることが、安心につながります。
最後に
「もし明日、長期入院が必要になったら?」
「もし家族が先進医療を選びたいと言ったら?」
こうしたシーンをイメージして備えておくことが、将来の安心をつくります。
あなた自身のライフプランに合った医療費対策、ぜひ一度見直してみてください