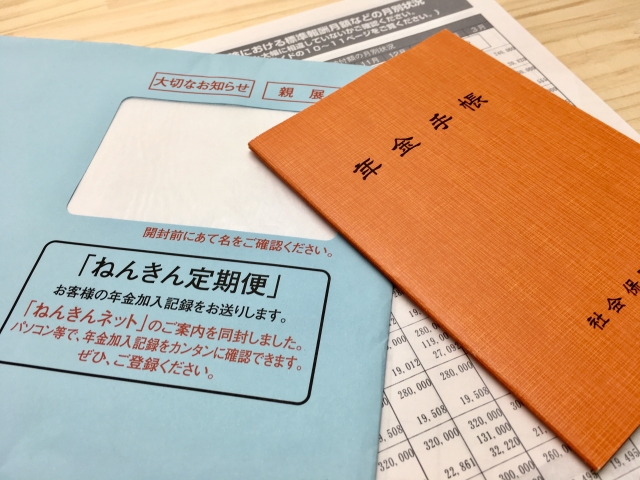2025.11.4 <00954>
1. 「ねんきん定期便」は“将来の安心を映す鏡”
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」。
60歳前後になると、これまでよりも詳しい内容が記載されるため、
「そろそろ本格的に見ておこうかな」と感じている方も多いはずです。
でも実際には、
「見てもよく分からない」
「金額が多いのか少ないのかピンとこない」
「この金額が本当にもらえるの?」
という声がとても多いんです。
ねんきん定期便は、**「年金の成績表」**のようなもの。
これを正しく理解しておくと、
「いつから、いくらもらえるのか」だけでなく、
「これからどう働くか」「どんな生活設計を立てるか」まで見えてきます。
今回は、そんな“ねんきん定期便”の正しい見方を、
ファイナンシャルプランナーの視点から、わかりやすく解説します。
2. まず知っておこう:「ねんきん定期便」は誰に・いつ届く?
ねんきん定期便は、20歳以上のすべての公的年金加入者に送られます。
郵送のタイミングは「誕生月」。
📅届く頻度と内容の違い
| 年齢 | 届く内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 20〜49歳 | これまでの加入実績 | 年金見込額の記載なし |
| 50〜59歳 | 加入実績+将来の見込額 | 現時点の働き方を前提に試算 |
| 60歳以上 | 年金請求手続き案内+最終確認 | 受給準備に直結する内容 |
特に50歳以上になると、
「今のまま働き続けた場合に65歳からもらえる年金見込額」が記載されるため、
老後の資金設計のベース資料になります。
3. ねんきん定期便の構成を理解しよう
封筒を開けると、たくさんの数字と専門用語が並んでいて戸惑う方も多いでしょう。
でも大丈夫。見るべきポイントは「3か所」だけです。
🔹① これまでの加入期間
上部に「これまでの年金加入期間」という欄があります。
ここには、自分が 国民年金・厚生年金・共済年金 に加入していた期間が記載されています。
例)
- 国民年金:120か月(10年)
- 厚生年金:360か月(30年)
→ 合計480か月(40年)
この「合計期間」が480か月=40年あると、
老齢基礎年金が満額(令和6年度で約78万円)支給されます。
つまり、加入期間を確認することは、
「満額もらえるかどうか」を判断する第一歩です。
🔹② これまで納めた保険料の総額
次に見るべきは「これまでの納付額」。
自分がいくら年金保険料を払ってきたかが一覧で表示されています。
ここを見ると、
「会社員時代にどのくらいの収入が反映されているか」
「国民年金だけの時期はどのくらいか」
などがわかります。
特に転職・自営業経験がある方は、
未納期間や免除期間がないかチェックしておきましょう。
「未納」があると、その期間分の年金額が減ってしまうため、
60歳までに「任意加入」や「追納」で補うことも可能です。
🔹③ 将来の年金見込額
一番気になるのがここ。
「老齢年金の見込額(65歳から受給の場合)」が記載されています。
例)
- 老齢基礎年金(国民年金):78万円
- 老齢厚生年金:120万円
→ 合計:年間198万円(=月16.5万円程度)
ここで書かれている金額は、
「現在の収入や働き方が65歳まで続いた場合の見込額」です。
つまり、今後働き方を変えたり、パートになるなど収入が減れば、
年金額も変わる可能性があります。
4. 「この金額、本当にもらえるの?」を正しく理解する
ねんきん定期便の金額を見て、
「これが確定した年金額ですか?」
と質問されることがよくあります。
実際には、まだ“見込み額”です。
年金額は、
- 物価や賃金の変動
- 加入期間の延長
- 働き方の変化(厚生年金か国民年金か)
によって、今後も変動する可能性があります。
つまり、「今のペースでいけばこのくらいもらえる」
という“参考値”と考えるのが正解です。
5. 見落としがちな注意ポイント
ねんきん定期便は、「金額」だけでなく、
“これからの準備”を考えるための大切な資料でもあります。
以下の3つをチェックしてみましょう。
✅① 加入記録の“もれ”がないか
昔の会社勤務時代や短期アルバイト時代の加入記録が抜けているケースがあります。
特に、厚生年金の記録漏れは意外と多いです。
- 勤めていた会社名が書かれていない
- 年金加入期間が短すぎる
- 国民年金の未納期間が思い当たらない
こうした不明点があれば、「ねんきんダイヤル」や最寄りの年金事務所で確認を。
加入記録は、過去の源泉徴収票や給与明細などで証明できます。
✅② 配偶者の“第3号被保険者期間”の確認
専業主婦(主夫)期間がある方は、「第3号被保険者期間」が記載されているかを確認。
ここが抜けていると、国民年金が未加入扱いになる可能性があります。
配偶者の勤務先での届け出が必要なケースもあるため、
「第3号になっていた時期」が正しく反映されているか要チェックです。
✅③ 年金の受給開始年齢と併給調整
65歳より前に繰上げ受給をすると、減額が一生続きます。
逆に、70歳まで繰下げると最大28%増。
また、厚生年金+企業年金などの組み合わせによっては、
支給額が調整される場合もあるので、
“もらい方の設計”を考えるきっかけとして定期便を活用するのがおすすめです。
6. “ねんきんネット”を使うともっと便利
最近は、紙のねんきん定期便よりも便利な方法があります。
それが「ねんきんネット」。
スマホやパソコンから、
- 年金加入記録
- 将来の年金見込額(繰上げ・繰下げ含む)
- 受給額のシミュレーション
などをいつでも確認できます。
登録は無料で、マイナンバーカードまたは基礎年金番号で簡単にアクセス可能。
さらに、「自分で条件を変えて試算できる」点が紙との大きな違いです。
たとえば:
- 65歳まで働いた場合
- 70歳まで延長した場合
- 年金を67歳からもらう場合
このように複数パターンを比較できるので、
“もらい方の損得”を自分で確かめられます。
7. FPが伝えたい「ねんきん定期便の使い方」3ステップ
年金定期便は、ただ「見る」だけではもったいない!
FPとしておすすめしたい活用法があります。
💡STEP①:数字を“家計表”に入れてみる
定期便に書かれている「年金見込額(年)」を12で割って、
月々の収入として家計表に組み込む。
現役時代の支出と比較して、差額を見てみましょう。
「今より月〇万円少なくなる」と分かれば、
老後資金をどのくらい準備すべきかが明確になります。
💡STEP②:夫婦で見比べる
夫婦それぞれの定期便を見比べると、
年金額のバランスが分かります。
例えば、
- 夫:厚生年金200万円/年
- 妻:基礎年金75万円/年
→ 合計275万円(=月約23万円)
こうして“世帯単位”で見ると、実際の生活設計がリアルになります。
老後は「世帯収支」で考えるのが鉄則です。
💡STEP③:ライフプラン(キャッシュフロー)と照らし合わせる
定期便の数字を、老後のキャッシュフロー表に反映させましょう。
「何歳までに貯金をどれくらい使うか」「どの時期に収支が赤字になるか」が一目で分かります。
老後資金は、“今の年金額+貯蓄の取り崩し計画”の掛け合わせ。
定期便の数字がその「出発点」になります。
8. FPがよく受ける質問Q&A
❓Q1. 金額が思っていたより少ないのですが…
→ 年金額は、標準報酬月額(現役時代の平均給与)で決まります。
パート期間や国民年金期間が長い場合は、金額が低くなります。
今後数年間働く予定があるなら、65歳まで厚生年金に加入する期間を増やすことで、少しずつ年金額を増やせます。
❓Q2. 「見込額」と実際の受給額はどれくらい違う?
→ 将来の物価や賃金変動を反映するため、数%上下することがあります。
ただし、大きく減るわけではなく、目安としては十分信頼できる数値です。
❓Q3. 夫婦の年金額は合算してもいいの?
→ 生活費の設計では“合算してOK”です。
ただし、税金・健康保険料は個人単位で計算されるため、
「世帯収入」「個人負担」の両方でシミュレーションすると安心です。
9. まとめ:「ねんきん定期便」を“未来設計の出発点”に
ねんきん定期便は、単なる通知書ではありません。
それは、あなたがこれまで働いてきた「人生の記録」であり、
これからの安心を描くための“道しるべ”です。
✅ 加入期間を確認し、もらえる資格を整える
✅ 将来の見込額を把握し、家計の見通しを立てる
✅ 夫婦で照らし合わせて、安心のキャッシュフローを描く
この3つを行うだけで、
年金への漠然とした不安は確実に減ります。
老後資金づくりは、「不安を消すこと」ではなく、
“安心できる根拠を持つこと”。
その第一歩が、まさに 「ねんきん定期便を正しく見ること」 なのです。